大阪万博記念写真館
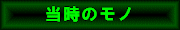
 携帯電話 ( 写真 ツーカー携帯電話 1997年ソニー製 )
携帯電話 ( 写真 ツーカー携帯電話 1997年ソニー製 )もちろん携帯電話はありません。電気通信館に展示されたワイヤレスホンがそのハシリだと思います。 今でこそ、電話は個人ごとにありますが、当時は各家庭に一本、黒いダイヤル式の電話機が主流でした。機能は通話のみで音量は固定。 着信音はジリジリリーン、ジリジリリーンと「本物」のベルが鳴りました。アラームになったのはいつからでしょうね。 短縮ダイヤルや着信履歴もなく、念のために言えば情報を表示する液晶パネルもありません。 したがって、電話機の前には必ず、電話のアドレス帳がぶら下がっておりました。 学校では緊急連絡の為に「連絡網」のプリントが配られ、発信元から次から次の人へとリレーで電話を架けて、最後に発信元へ電話をする。これで連絡完了です。 日本電信電話公社がすべての電話事業を運営していて、今のように民間電話会社はありません。  プリントには電話番号以外に住所も書かれていました。当時は個人情報についてのセキュリティの考えはあまりありません。 大量の情報をあらゆる所に伝達する手段は、テレビや新聞ぐらいで、「紙」のメディアでは現在のように局地的な情報でしか なかったですね。受話器は口臭が付くので、香水入りの穴あきのカバーが付けられたり、電話機に布カバーが着せられたもの もありました。プッシュホン電話機はこのころ登場しています。 遠い所の人と友達になってコミュニケーションを取る手段としては、手紙による「文通」が盛んでした。 趣味の雑誌の巻末には、必ず文通希望のページがあって、共通の話題で友達になるのです。 このような友達をペンフレンドと呼びました。異性との文通が人気でしたね。 ( 写真 プッシュホン電話 1997年NTT製 ) |
 テレビ ( 写真 ナショナルパナカラー19型 撮影 1970.11)
テレビ ( 写真 ナショナルパナカラー19型 撮影 1970.11)ようやくカラーテレビが普及し始めた頃です。うちは比較的早く、昭和43年にナショナルパナカラーを買いました。 飛騨川バス転落事故のニュースがカラーで放送されていて痛ましさが生々しく感じられたのを憶えています。 おかげで、万国博の映像や番組などもカラーで見ることが出来ました。夜、10時くらいから三菱提供の特集番組がありましたね。 アポロ11号の月着陸もこのパナカラーで見ました。このときの月面からの中継は白黒放送です。 初期のパナカラーは真空管が使われていました。寒い日はなかなか映りません! テレビを見るにはスイッチを入れます。(当たり前)スイッチはつまみを引き出します。それから必ずカラー調整を行います。 最初に映る映像はすごくにじんだ見づらいものです。 チャンネルダイヤルの周りに銀色のリングがあって、これを押すと画面に縦の緑色の帯が映ります。 リングを押しながら廻すと帯の幅が細くなって行きます。もっとも細くなった所で鮮明な画像になるのです。 この緑の帯をナショナルでは「マジックライン」と呼んでいました。 しかし、これからが微調整のウデの見せ所です。 テレビの全面パネルにはいくつかのダイヤルがあって、色相、色の濃さ、コントラスト、輝度を調整します。 調整がおかしいと、人の顔が黄緑色になったり、ムラサキ色になったりします。気持ち悪かったですね。 まもなく、オートマチック機能が開発されて、ボタンを一回押せば、適正カラー調整が行われる機種が発売されました。 テレビは家具調で木製でした。そして大きな物でした。19型のパナカラーは奥行きが50センチぐらいありましたね 家庭用ビデオも無く、本放送を見逃したらアウトです。まだリモコンが普及する前だったので、チャンネルダイヤルを 直接手で回して番組を変えます。テレビは高価で一家に一台の時代でしたから、「チャンネル争い」という言葉が生まれました。 ドラマ「細うで繁盛記」やアニメ「サザエさん」「ムーミン」なんかが放映されていたのもこのころです。 学校では夏休みの心得に「テレビに心を奪われずに勉強すること」と書かれていましたよ。 それはテレビッ子にはムリな相談というものです。 |
 カメラ ( 写真 ミノルタハイマチックC 1969年発売 )
カメラ ( 写真 ミノルタハイマチックC 1969年発売 )
デジカメが登場したのはずっと後年のことです。 現在「銀塩写真」と呼ばれているフィルムカメラしかありません。また、ようやくカラー写真が普及し始めた頃でした。 35㎜フィルムにはネガカラー、リバーサル(カラースライド)とモノクローム(白黒)があり、カラーフィルムの感度は ASA100(ISO100)が最高でした。国産白黒フィルムの感度はASA100がSSで、ASA200がSSS(スリーエス)と呼ばれました。 カラーフィルムは12枚撮り、20枚撮り、36枚撮りの3種類で、24枚撮りフィルムは後年登場の規格です。 私が使っていた「ミノルタハイマチックC」は当時流行したコンパクト35ミリEEカメラです。EEとは「エレクトリックアイ」 (電子の目)という意味で、本機は新式のcds(硫化カドミウム)メーターを搭載し、F2.7の準広角レンズを持っていました。 当時のカラーフィルムはデリケートでこのような電気露出計内蔵の自動露出コンパクトカメラがカラー撮影の普及機だったのです。 このカメラは昭和45年4月にお小遣いをためて買いました。14000円だったから、中学生には高価なものでした。 レンズ交換が出来る一眼レフカメラは最低でも25000円していましたから、スティタスですよ。 いまではズームレンズは当たり前ですが、当時は特殊なものを除いて標準単焦点レンズが当たり前でした。 ストロボは単体で一番安い物でも6000円くらいで単三電池2本で50回くらい光りました。 なお、ストロボもようやく普及しはじめたころで、ストロボ内蔵のカメラはありません。 写真に日付けが写る最初のカメラ「キャノデートE」はこの年の発売です。オートでなく、日付はダイヤルを手で回して合わせます。 万博にはフィルムをカラーと白黒を一本ずつもって行き、カラーは色のきれいなものに限って写しました。 カラー写真の被写体に「虹の塔」が多いのはそのためです。お金がかかるのでなかなかシャッターを切れなかったですね。 オートフォーカスもありません。ピントは距離計やピントグラス、あるいは目測で決めます。 電気露出計がないカメラは、シャッター速度や絞り値は、カンと経験がすべてです。 写真に失敗はつきもので、まともな写真を撮るには勉強が必要とされた時代でした。 |
 腕時計 ( 写真 セイコーファイブアクタス 1969年発売 )
腕時計 ( 写真 セイコーファイブアクタス 1969年発売 )
スイス館で初めてクオーツ腕時計が紹介されていました。四角い時計でした。 ただし、クォーツ腕時計は始祖鳥的存在で、一部の電子音叉腕時計(電磁石で作動する音叉の振動回数が歯車に伝わる) などを除いては殆ど自動巻もしくは手巻き(ゼンマイ動力)の腕時計の時代です。 誤差は一日プラスマイナス30秒ならば良くあってると言えます。毎日時報で修正してましたね。 腕時計の文字盤には「23JEWELS」などの表記があって、JEWELSとは時計の内部に使われている宝石の事です。 宝石は人工ルビーです。歯車の心棒の軸受け部分が円いルビーでできていて、中央に小さな穴が空いていて、 この穴で心棒の先端を受けます。この部分が金属なら長く使用すると摩耗で穴が広がって回転の誤差が大きくなります。 ルビーはダイヤモンドの次に硬いので、摩耗が無く、機械的精度が保てると言うわけです。 したがって、このルビーの数が多ければ多いほど高級な時計でした。普及品で17石、高級品では40石ぐらいでした。 この頃の時計は定期的に分解掃除をするのが常識で時計屋さんはメンテナンスが大きな収入源だったのです。 腕時計に注すオイルは動物性で、トナカイの蹄の脂やゴンドウクジラの脳の脂が原料でした。 これらの動物は極地に棲むため、脂は不凍性です。 寒冷地でも機械時計が安定して作動するためには最高級のオイルとされていました。 腕時計は高校生になったら入学記念に贈られるのが、当時の国民的習慣でした。一万円前後しました。 だから銭湯に行ったら番台に時計を預けたものです。 セイコーやシチズン、オリエントなどの自動巻防水腕時計が人気で、文字盤は銀白色、青や緑のメタリックもありました。 テレビの時報は「セイコーの時計が○時をお知らせします」でCMを兼ねていましたね。 大阪万博には祖父からもらった「セイコースーパー」をはめて歩いていました。写真館に時間が記載されているのは、そのおかげです。 デジタル液晶腕時計は実用化されていなかったので万博会場にもありませんでした。念のため。 |
 電車に乗る ( 写真 阪急万博西口駅 撮影1970.9.13 )
電車に乗る ( 写真 阪急万博西口駅 撮影1970.9.13 )
祖父は阪急電鉄に勤めていました。 阪急電鉄の社史を綴った本によると日本最初の自動改札機は昭和42年3月1日に 阪急北千里駅に設置されたものです。しかし、大阪万博の頃は多くの駅で駅員が改札口に立っていました。 キップは自動販売機で買うか、窓口で直接買います。お金やキップをやりとりする台は石で出来ていました。 未だ、磁気券が普及していなかった時代なので、回数券は同じ券が11枚綴りです。これで10回分の料金でした。 改札で長く連続したキップを一枚ずつちぎって使ったように思います。定期券は普通の紙の券に期日をハンコで押してありました。 祖父から聞いた駅改札の話をひとつ。 悪い心をもった人は必ず居ます。定期券は普通の紙で、改札で駅員が日付を確認するわけですから、これをペンなどで 書き換えて改ざんするのです。実際にはすごく上手に改ざんする者もいたそうです。 しかし、改札員はあまり、定期券を見てる様には見えません。時には全く見てない様に見えます。 サボっているわけではありません。理由があります。 どんなに早く通過する定期券もスローモーションを見るように見えていると言います。さらに、 改札を通過する乗客の定期券の期日は改札員が記憶しているからです。多くの乗客の差し出す定期券でも毎日見ているうちに そのお客が通過する時間はもちろん、名前はおろか定期券の生年月日まで掌握してしています! 「もしもし」 期限切れに気が付いていない客はそこで気が付くのですが、不正をしている人は大声を出して怒り出したり、 一目散に逃げたり、もう大変ですね。定期券を指で隠して出したり、そわそわしたりで、そぶりがおかしいです。 祖父はお客の表情や態度で不正を見抜くと言っていました。 そして、不正をした人は罰則にしたがって多額の乗車賃を支払う事になります。ワリに合わないですね。 今は、改札はコンピュータの時代ですが、どの程度不正を見抜いているのでしょう。 大阪万博頃の電車は冷房車が少なく、夏は暑かったですね。 |
 テレビゲームなど ( 写真は、ゴライオンのカルタ 1981年 )
テレビゲームなど ( 写真は、ゴライオンのカルタ 1981年 )
大阪万博の古河パビリオンやIBM館にはテレビゲームがあったらしいですが、私は覚えていません。 家庭用のものは未だありません 万博に展示されたくらいですから。 テレビゲームを初めて見たのは2年くらい後の近所の銭湯です。 テニスと呼ばれていたもので、画面では発射される球(四角い点)が飛んできて、それをカーソルで打ち返すゲームです。 打ち返せなかったらアウト。100円で3回くらい遊べましたね。 画面は最初はモノクロだったように思います。無音でした。 それまでの家庭用ゲームはニューバンカースやダイヤモンドゲーム、軍人将棋、スゴロク的なものの時代でした。 半機械的な物はエポック社の魚雷戦ゲームや手で人形を操作するサッカーゲーム、磁石で動く競馬ゲーム、 小さな鉄球をミニチュアのバットで打つ野球盤、ルーレットなどなど。 サイコロなどを使った物理的なゲームでした。 遊園地やホテルではハンドルで車の模型を運転する遊戯機械、透明ドームで玉をシュートし合うバスケットボール アフリカで動物を狩りする射撃ゲーム、すべて機械式でした。 喫茶店でスペースインベーダーが登場したのは8年ぐらい後のことです。 当時のゲームは子どもの遊ぶ物ですべて健全なものでした。 現在のコンピュータのゲームは楽しいものがある反面、殺伐とした内容のものが多いので頂けません。私は。 |

 缶ジュース
缶ジュース( 写真は、ミリンダ、コカコーラ、ペプシコーラ、ファンタ 昭和40年代 ) 今は自販機が普及して、ペットボトルの飲料も増えましたが、1970年ごろは今ほど缶飲料はなかったですね。 当時はスチール缶ばかりで、紙コップのジュース自販機やガラスビンの自販機もありました。 ビンの飲料のフタは王冠ですから、自販機に固定された栓抜きであけて、その場で飲んでしまいます。空き瓶は横の木箱などに戻していました。 ペットボトル型のものは無かったので、栓をあけたら持ち歩くことは出来なかったですね。 ジュース類の価格は50円か60円くらいだったと思います。万博会場にはクラウンコーラの紙コップ自販機があって、値段は50円でした。 たしか、氷が出ましたよ。 250mlの缶が多かったです。ミリンダは、ストロベリーやメロン、ファンタは、グレープやオレンジなどがありましたが、いずれも無果汁でした。 これらの無果汁ジュースは猛烈に甘くて、飲んだ後、着色料で舌が赤やムラサキ色になりましたが、とくに気にしなかったです。 現在では着色料の濃さや甘さは、ほどよい味わいになっていると思います。 缶はすでにプルタブになっていましたが、アルミのフタがリングと一緒に完全に取れてしまうタイプです。 それよりも以前の時代のものは、缶に小さな缶切りがついていて、この缶切りで缶に穴をあけて飲んだのです。 今のように缶入りのお茶はありませんでした。お茶は家庭で飲むものでしたから、缶入りで発売しても売れなかったと思います。 分別回収も普及していませんので、「空き缶はくずかごへ」と書いてありましたね。 
1968.4.8 宝塚で (子どもの野球帽は巨人軍がふつうでした) |

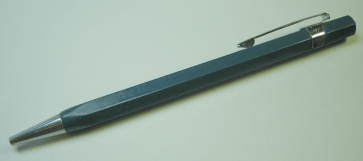
文房具 (写真左から ゼブラボールペン、モリソンと三菱のシャープペンシル、学研サムノック ) 今は100円で買えるシャープペンシルも、1970年頃の値段は500円でした。万博の入場料は大人が800円だったので小、中学生には高価な文具でした。 私は小学校5年の時にシャープペンシルを叔父にもらったのが最初の出会いです。芯は0.9ミリで、黒と赤の2色でした。 そのころのシャープペンシルはノック式ではなく、軸を回すと芯が出る繰り出し式で、芯は細いパイプで出来たホルダーに直接差し込んで固定します。 芯が短くなるとパイプについてある細いピンをスライドさせると芯の残りがポロリと出てきます。 ノック式の物は1970頃に普及して、芯も0.5ミリと細くなりました。芯の値段は20本くらい入って100円でした。 先端のパイプがスライドして後退するものや、横ボタンで芯が出る「ペッカー」という商品もこのころの発売です。 写真の学研サムノックは芯ホルダーで、付属の芯削りを使って、先端を常にとがらせる必要がありました。値段は300円だったから手ごろでしたね。 このホルダーは外殻だけが私の引き出しに残っていたものです。これは1970年に買いました。 ボールペンはルビーボールのものもありました。安価なビッグボールペン(使い捨て)は50円で、三菱ボールペンは30円でこれに対抗しています。 これらは青や赤、黒、などのきれいなプラスチックとピカピカの金属軸とのコンビネーションで学校近くの文房具店のガラスケースに飾られて、欲しくていつも下校時に見ていました。 買った日はうれしくて枕元に置いて寝て、筆箱の中に大切に温存されてしまい、当分のあいだ実戦にはほとんど参加しませんでした。 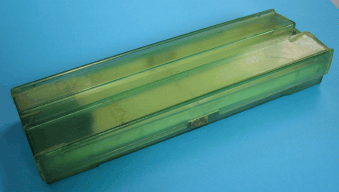 アーム筆入れ (1968年購入)
アーム筆入れ (1968年購入)
「象が踏んでもこわれない」テレビコマーシャルを見た6年生の私は、迷わずアーム筆入れを買いました。実際に筆箱を踏んでも壊れないので満足した子どもでした。 これも300円したので、高かったです。怪獣ガメラのプラモデルは300円くらいでしたから。 フタの真ん中に飾りで付いていた鎖は脱落していますが、未だに捨てられないでいます。高校卒業まで使っていました。 まだ、セルロイドの筆箱(写真下 昭和40年代後半)は売られていました。セルロイドはあらゆるプラスチックの中でも軽く、独特のきれいな色のものが多いです。 これは最後期のものだと思います。きれいな水色が気に入って当時買いました。セルロイドは割れやすいので、あまり使用しなかったために残りました。内部は二段になっていて、引き出し式 になっています。トンボ鉛筆や三菱ユニが入ったままです。 セルロイドは熱に弱く、火がつくと爆発的に激しく燃え上がるので火気厳禁です。 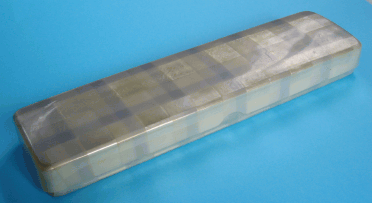
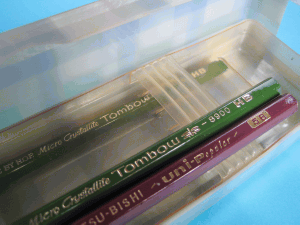
|
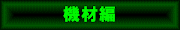 |
 |
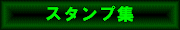 |
=現在地= | 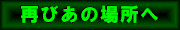 |
EXPO'70の頃へ戻る
大阪万博 記念写真館へ戻る